セパレーターのピッチや位置、どうやって決めていますか?
型枠図面に細かく書かれていないことも多く、現場で「これでいいのか?」と不安になることもあると思います。
本記事では、20年の現場経験を持つ型枠大工の視点から、セパのピッチや位置の基本ルールや現場での注意点を、初心者さん向けにわかりやすく解説します。
トラブルややり直しを防ぐためにも、セパの知識は必要です。
セパレーターの役割を簡単に理解しよう
• コンクリートの厚みを保つために必要な金物
• 型枠をつなぎ止める、型枠が膨らまないようにする
セパレーターの太さは基本5/16(2分5厘ニブゴリン)
土木など、より強度を上げたい場合は3/8(3分サンブ)を使います。
セパレーターの基本ピッチは?|標準の目安
• 基本のピッチ:450mm〜600mm
• スラブや梁の大きさ・コンクリート圧により調整
• 荷重が大きい場所や打設時の圧が強くなる場所は300mm程度にすることも
📌 ポイント
セパが広すぎると型枠が膨らんで仕上がりに影響
狭すぎると手間と材料コストがかかる
⸻
セパの簡単なピッチの決め方
・壁の厚み・高さ・コンクリートの流し込む回数によって変わります
[壁の厚み]
厚みが小さければ側圧は少ないし、厚みが大きくなれば側圧も大きくなる
※大きすぎると(2m以上)側圧が減る。
コンクリートは水と違って少しドロドロで1箇所に出すと山になるため。
大きいとそれだけ、コンクリが入るのに時間がかかるため。
[高さ]
1800mmの高さの壁と、3600mm、倍近く側圧がかかる
[コンクリートの流し込む回数]
3600mmの壁を2回に分けて打設すれば1800mmの壁と同じ側圧しかかからない(1回打設後1時間あけると安心です)
上記の内容から↓
1800mmの壁は600ピッチで問題ない
3600mmの壁は450ピッチ(1800mmより上は600ピッチでも問題ない)
3. セパ穴の位置決めの基本|やりがちなミスと対策
• 内側の角から150mm以内にセパはとらない(ホームタイの長さが150mmなのでホームタイどうしが干渉するため)
• 角から300mm以上離れるとパンクや膨らんだりする
• 高さはコンクリから100とか50とかキリのいい数字はだいたい鉄筋の横筋に当たる
• 梁があるときは梁下から50mmまで。それ以上は梁筋を組むときに邪魔になる
• はじのセパは(柱の角や壁の始まり)50mm以上にすること。30や40だとカブリがとれないため
📌 アドバイス
穴位置は加工場で開けてしまっても問題無いですが、柱の中に通すセパの位置は現場を見て開けた方が直しが少ないと思います。
柱筋は太くて動かないので、壁ならなんとかいけるかも…
壁厚が300以上は現場で開けた方が吉です。
⸻
スラブや鉄筋からセパをつなぐ場合の考え方
• スラブからセパをとるときはスラブ下から20mm上げて穴を開けてください
• スラブからセパをとるときはスラブコマを使ってください。セパが長くてスラブのカブリがとれない場合はスラブコマのハイPコマH-30を使ってください
• 鉄筋からセパをとるときは側圧によって繋げる金物が変わります。
足元の力がかかる場所の場合はKSガッツを使って下さい。
スラブ段差などちょっとした場所ではドマスターがおすすめです。
セパ穴のサイズと穴埋め方法
穴のサイズはみなさんバラバラだと思います。色々考え方があると思いますが、ボクの考えを載せときます。
基本穴径10.5mm→どうしてか?
そもそもセパのサイズが8mmぐらい(2分5厘)なので、これより大きいサイズだと取り付ける際にセパがポロポロ落ちてしまいます。(立っている型枠にセパを刺したとき)
ボクのセパレーターフックだと10.5mmでもやりやすいです。これより小さいとセパフックが使いづらい、逆に大きいとやりやすいけど、セパ付けの際ポロポロ落ちてイライラします。
デメリットもあります。
セパ穴を間違って穴埋め作業が必要になったとき、 12mmのキリで開け直しが発生します。
•間違って穴をあけてしまったときは?
プラスチックの穴埋め(プラセン・つめせん)を叩いて塞ぎます。
プラセン(つめせん)は12mm用がほとんどだと思います。
セパ穴10mmなら12mmに開け直して下さい。
⸻
✅まとめ
セパレーターのピッチや位置決めは、型枠の精度や安全性、仕上がりに大きく影響します。
初心者の方にとっては悩みどころですが、基本を押さえればミスは防げます。
じゆたまブログでは、こうした“現場で本当に役立つ型枠の知識”をこれからも発信していきますので、ブックマークやシェアしていただけると嬉しいです!
📘 おすすめ学習コンテンツ
🔹 図面が読めるようになる基礎講座(note)
図面の基本記号・読み方・スケッチ解説までをまとめた入門セット。
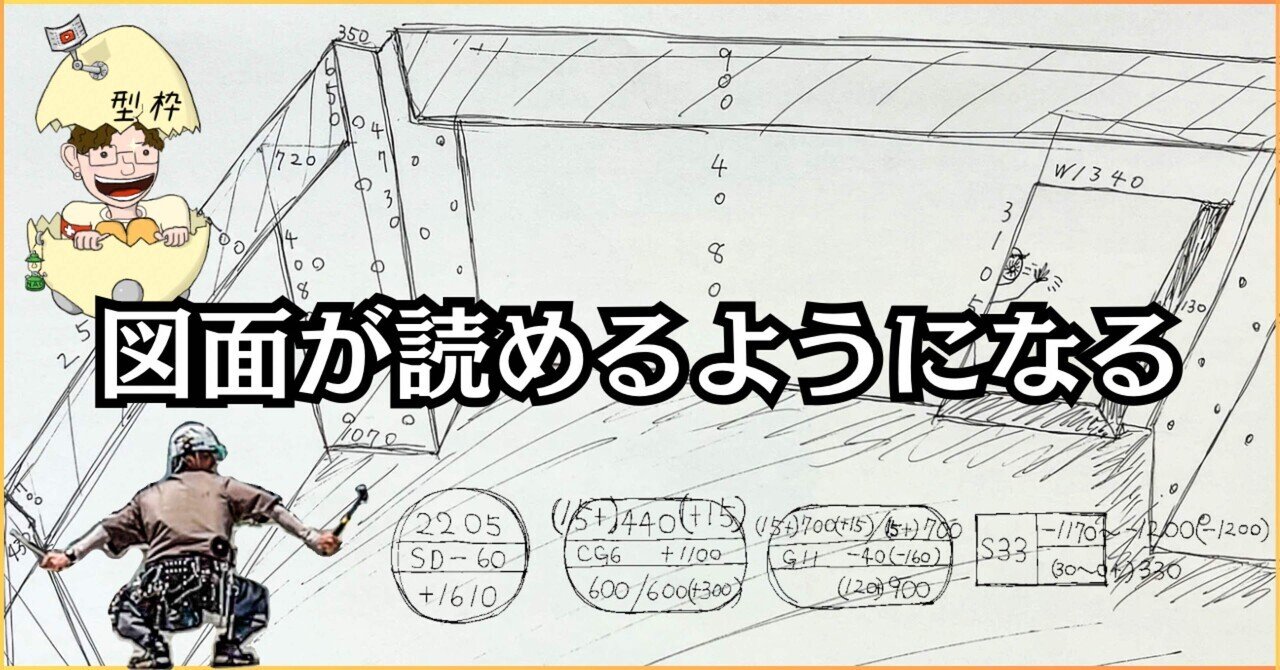
🔸 型枠拾い出し 完全マスターガイド(note)
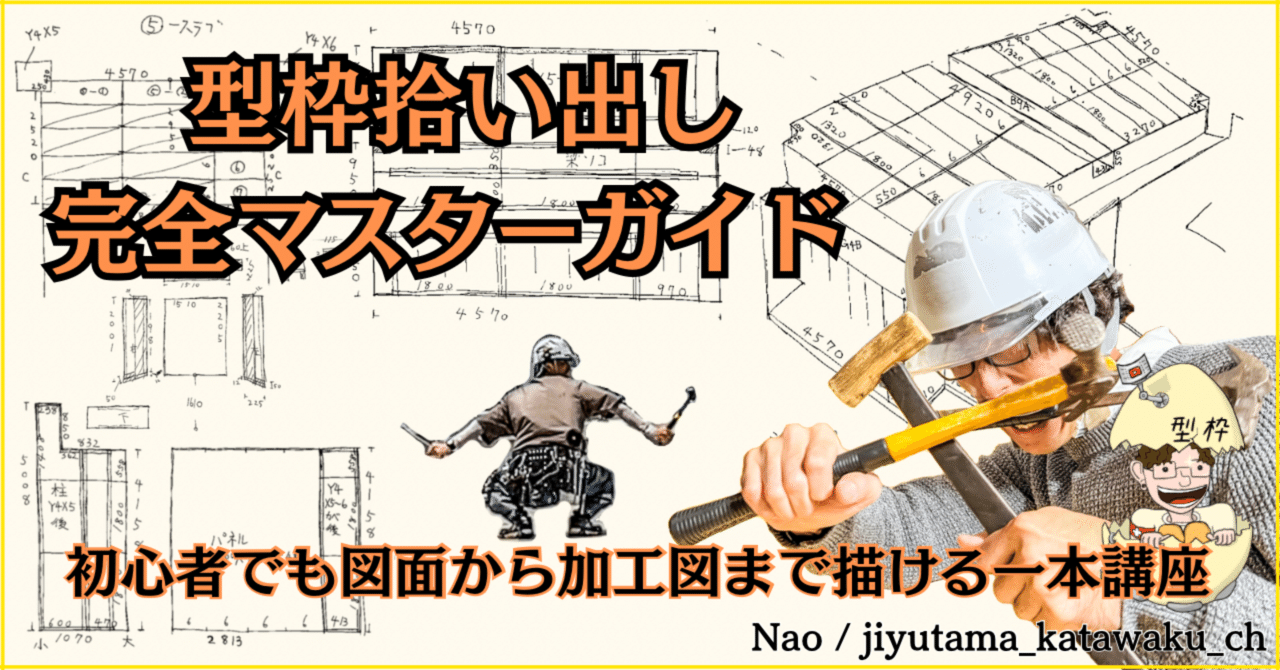
型枠のYouTubeもしています
じゆたまの型枠チャンネル↓↓↓
お知らせ用X(旧Twitter)
じゆたま↓↓↓




コメント