今回は、梁(はり)と開口部(ドア・窓など)の加工図の描き方を解説します。
現場で迷わない、わかりやすい図面のコツも紹介します。
梁(はり)の加工図とは
梁はスラブと柱をつなぐ構造体で、建物の骨組みを支える重要な部分です。
加工図では、様々な要因でやり方が変わります。
加工図に影響する要因

① スラブの施工方法による違い
スラブのやり方によって梁底(梁下)を大面(のっけ)にしたり、小面(挟み込み)にしたり、変わります。
それと、梁側に縦桟木を入れる、入れないも変わります。

[スラブ施工方法による違い]のPDF画像です。使って下さい☺︎
② 梁の取り付け方法による違い
梁の取り付け方法によっても梁の作りが変わります。
足場支保工で梁を受ける場合も変わります。

[梁の取り付け方法による違い]のPDF画像です。使って下さい☺︎
✅最終判断まとめ
梁加工図拾い出し前に必ず目を通すこと!
↓↓↓

梁加工図の描き方手順(基本の流れ)
①:梁記号を確認
②:イメージ図を描く
③:寸法を入れる(外周)
④:ベニヤ割付を考える
⑤:桟木の配置
⑥:番付を記入
①:梁記号を確認
梁の形状・サイズ・を図面でチェック。
②:イメージ図を描く
梁と繋がる柱の位置関係を簡単にスケッチ。
③:寸法を入れる(外周)
梁の外形寸法を正確に記入。
④:ベニヤ割付を考える
ベニヤどう使って型枠を作るのかを、わかるように書きます
ニロク2×6 or サブロク3×6どっちのベニヤを使うのか?
パネルを使うのか?
⑤:桟木の配置
強度と施工性を考えて桟木の位置を決める。
⑥:番付を記入
梁と繋がる柱の番付も合わせて書き、組み立てやすくする。
完成です♪

開口部(ドア・窓など)の加工図の描き方
開口は入り口や窓、小さな穴など色々あります。
窓サッシが取り付く部分はコンクリートを削って調整する必要があるため、あらかじめ型枠にアンコ材を取り付けて“ダキ”を作っておく。など、かなり複雑なので詳しく解説します。
・SD開口・AW開口・腰壁付き開口
開口加工図の描き方手順(基本の流れ)
①:開口記号と壁厚・ダキを確認
②:イメージ図を描く
③:寸法を入れる(外周)
④:ベニヤ割付を考える
⑤:桟木・アンコ材の配置
⑥:番付を記入
①:開口記号と壁厚・ダキを確認
開口記号で開口の高さ、幅。見上げ図で壁厚とダキ・面木・サッシアンカー有無を確認する。
②:イメージ図を描く
開口上下と左右の型枠の絵を描く
アンコの絵も一緒に
開口は上下の枠を大面にして下さい
③:寸法を入れる(外周)
壁の厚みが開口枠の幅
左右の枠の長さは天端に上の枠が乗るのでマイナス12(ベニヤ分)
上下の枠は開口記号の幅(W)の寸法
ダキの形状は図面の詳細を確認
腰壁は勾配がつくことがあるので、図面の詳細を確認
④:ベニヤ割付を考える
開口上下の枠はベニヤが一枚ものだと問題ないのですが、長さが足りなくて補助ベニヤを入れる場合、あんまり小さいサイズだと、取り付ける際に壊れてしまうので最低でも300以上にして下さい。
左右の枠の下端が斜めの場合やダキがつく開口は補助を下にして下さい。
⑤:桟木・アンコ材の配置
左右の枠は長手に桟木、壁厚が300を超える場合は天端、下端も桟木。
上下の枠は大面なので120バックして下さい。
⑥:番付を記入
開口記号の名前を入れます
上下左右も入れて下さい。
完成👍🏼
手書き加工図をきれいに描くコツ
手書きの加工図は、基準線と名前欄をあらかじめテンプレート化すると時短になります。
• 通り芯(A通り・1通り)を基準線として入れる
• 名前欄:部位名・日付・作成者を記入
• 枠線やスケールを揃える
🧩 PDFテンプレート化しておけば、毎回の下書きが不要になります。
加工図用のテンプレート配布中↓↓↓
まとめ
梁はスラブや取り付け方法によって加工が変わる
開口は記号だけではなく、詳細図も確認すること
📘 おすすめ学習コンテンツ
🔹 図面が読めるようになる基礎講座(note)
図面の基本記号・読み方・スケッチ解説までをまとめた入門セット。
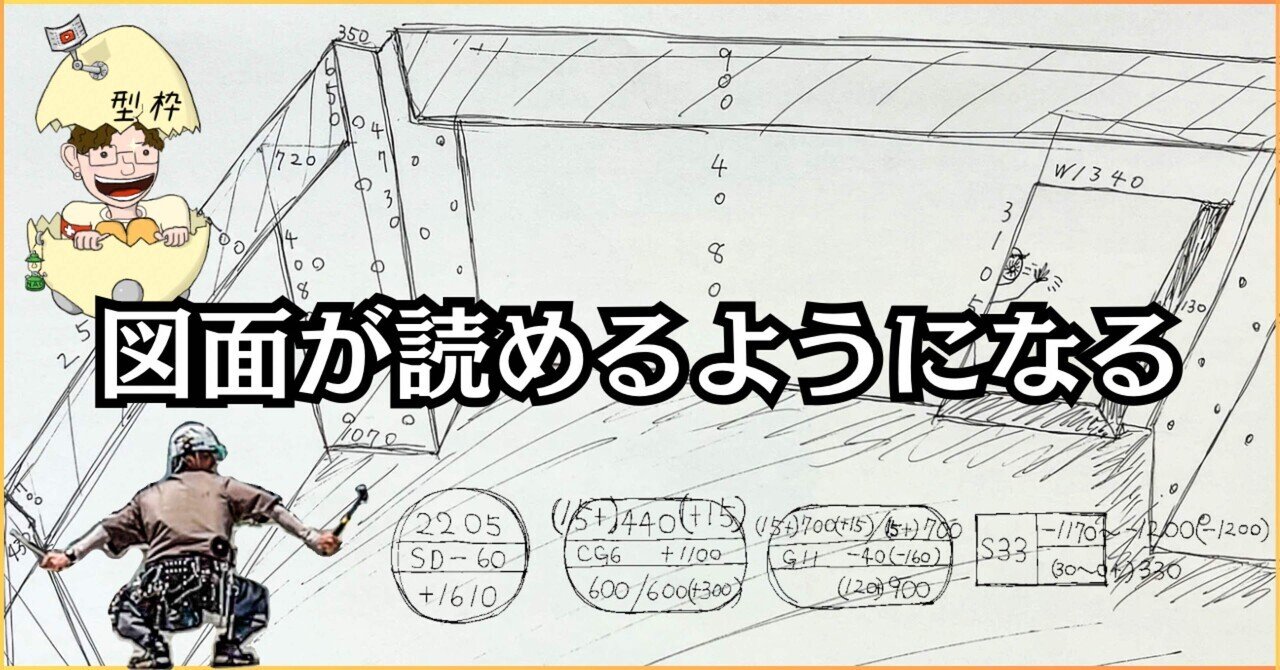
🔸 型枠拾い出し 完全マスターガイド(note)
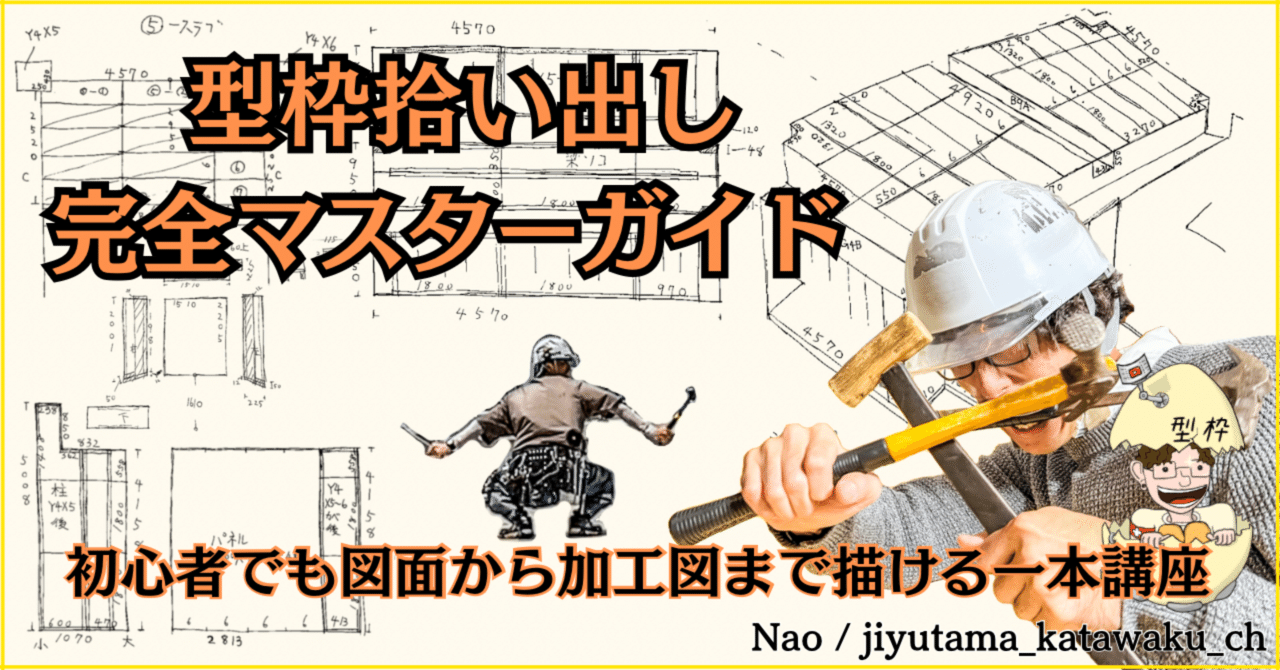




コメント