はじめに
前回の「拾い出し入門①」では、型枠材料の基本と“ばんづけ”の考え方について学びました。
今回は、柱と壁の拾い出しをやる上で欠かせない「大面と小面の考え方」を解説します。
拾い出しで最初につまずくのが、
「どっちが大面?」「小面って何?」という部分。
ここをしっかり理解しておくと、拾い出しが一気にスムーズになります。
大面と小面とは?
まず、型枠では「大面(だいめん)」と「小面(しょうめん)」という言葉をよく使います。

角にくるベニヤのつけ方です。
躯体の形と同じ大きさのベニヤでは、角の収まりが悪く、躯体の形を上手に囲むことができません。
■ 大面(だいめん)
→内角(四角形の内側の角)なら先に角までつけた方が大面
外角(四角形の外側の角)なら被さる方が大面
■ 小面(しょうめん)
→内角なら大面の後につける方、大面のベニヤにぶつかる側
外角なら角で止まる側、被される方
拾い出しの基本の流れ
①:シキサンレベル
②:大面小面
③:イメージ図
④:寸法入れ(外周)
⑤:ベニヤ割付
⑥:桟木
⑦:番付
[①シキサンレベル]
型枠はコンクリートの上にそのまま建てたりはしません。
コンクリートの上はクリームの上みたいに水平ではありません。
なので、一度水平に高さを揃(そろ)えてから、建て込みをします。
そのことを「シキサン」と言います。
シキサンを詳しく知りたい人はココから飛んでください✈️
シキサンの高さの決め方を迷ってしまうと思うので、ボクのおすすめを載せときます。
床のコンクリートが捨てコン
(捨てコンクリートとは?土の上で鉄筋を組んだり、型枠を建てたりはできないので、土の上にコンクリを流して平らにしたもの)
の場合は捨てコンの高さから「40」上げたレベルをシキサンの高さにします。
躯体のスラブより精度が悪いのでベニヤ分の厚さ分、余計に高くしています。
躯体のスラブの上にシキサンをするときはスラブレベルから「30」上げたレベルをシキサンの高さにします。
捨てコンより精度がいいので30で丁度いいです。
シキサンの高さを決めたら、型枠の高さもシキサンに合わせて決めます。
[②大面小面を決める]
大面小面の決め方は「側圧」と「やりやすさ」
基本は通り芯のY方向は大面、X方向は小面みたいな感じで決めときます。
側圧(コンクリを入れたときに下ではなく横にかかる圧力)がこっちの方が強いなと、思った箇所(かしょ)は大面にしたり、小面だとやりづらい箇所は大面にしたり、調整します。
内側の角の場合は大面の方が側圧に強いです。
[③イメージ図を描く]
柱の首が右か左か?
途中から梁の高さが違っていたり、段差があったり、しますので、ざっくりでいいのでイメージ図を描きます。
大面小面もわかるように絵の中に入れます
[④寸法入れ(外周)]
大面小面の関係で、躯体寸法からベニヤ厚分を引いたり、型枠の厚さ分を足したり、計算します。
⑤:ベニヤ割付
ベニヤ2×6(ニロク)や3×6(サブロク)の配置をします。
[⑥桟木]
桟木の入る箇所がわかるように描く
[⑥番付]
できた加工図に名前を書きます。
どこで使う型枠なのか?がわかるように、通り芯や前後左右を書き入れます。
柱・壁の拾い出し
柱には梁がつくことがほとんどです。
柱枠と梁の枠が繋がる場所を「柱首」と呼んでいます。
柱首は小面にして梁を大面にして下さい!
梁の下も!
梁は柱に乗っかるものです。必ず梁が柱枠に乗るように大面にして下さい。梁の取り付けをするときにやりづらくなってしまいますし、収まりも悪くなります。
*独立の柱

拾い出しの基本の①〜⑥の流れで拾い出しをするのですが、独立の柱で気をつけることは、
大面小面を決めるときに向き合う枠の大面小面を同じにすることです。
セパ穴をあけるときに向き合う2枚の枠を重ねて同時に穴あけをするためです。
後は建て込むときに間違いが少なくなります。
*壁付きの柱

同じく基本の流れで拾い出します。
気をつけることは、こちらも大面小面です。
壁と柱では、柱の方が側圧が強いので、柱を大面にして下さい。
*壁の拾い出し


壁は梁下の壁やスラブ下の壁、外周の壁エレベーターの壁などがあります。
基本は同じです。
壁は横幅が長いものもあるので、パネルを使います。
毎回作っていたらすごく大変なので…
それとなるべく、パネルが角にこないようにします。
コの字の壁の内側なら両角に補助枠を入れて、パネルが角にこないようにします。
パネルが角にきてしまうと、解体するときに壊れやすいのと、単純に角の建て込みをするときにパネルは重くて、大きいので、やりづらいからです。
*袖壁(そでかべ)の拾い出し
袖壁(長い壁から出ている短い壁のこと)
よくバルコニーの端っこにあります。
袖壁は長手方向にセパが取れないことが多く、なるべくセパが取れなくても側圧に耐えられるように、止め枠の方は小面、長手は大面にします。
まとめ
今回は
・大面小面の考え方
・拾い出しの基本の流れ
・柱・壁の拾い出しをしました。
📘 おすすめ学習コンテンツ
🔹 図面が読めるようになる基礎講座(note)
図面の基本記号・読み方・スケッチ解説までをまとめた入門セット。
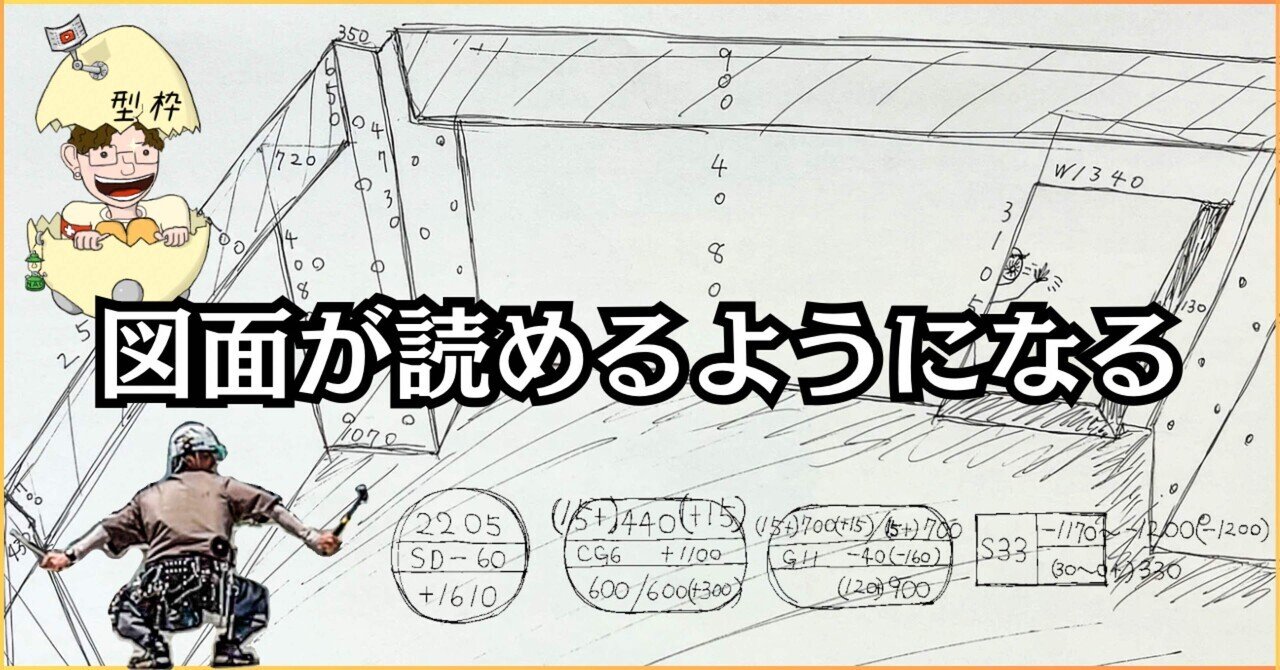
🔸 型枠拾い出し 完全マスターガイド(note)
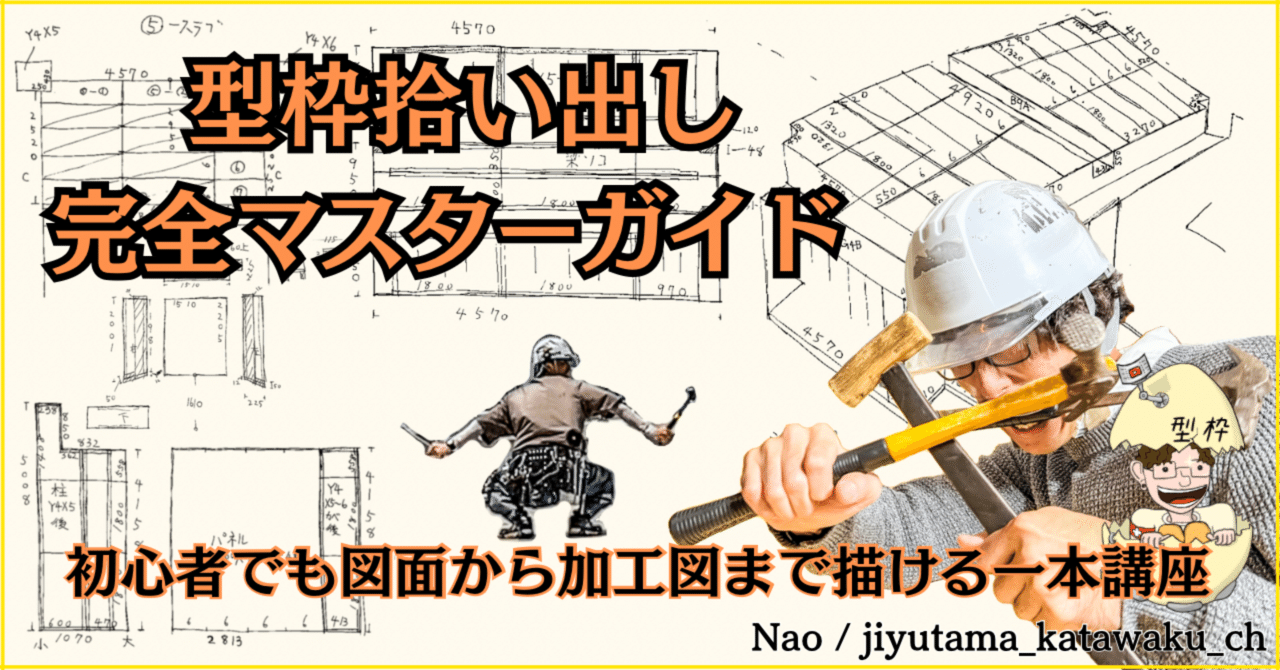
作図用PDF画像

動画内で使っていた用紙です。サイズはA4印刷の仕方でA3でも印刷できます。
SLラインや名前、日付を書ける線が書いてあります。
拾い出しに使えるPDF画像です。印刷して使って下さい↓↓↓📃
https://goldnao.com/wp-content/uploads/2025/10/3688dc116da36476b12085b9d2c5f40f.pdf
じゆたまの型枠チャンネル↓↓↓
お知らせ用X(旧Twitter)
じゆたま↓↓↓




コメント