コンクリートの建築現場に配られる図面を見て、
「どこから見ればいいのか分からない」
「床伏図と見上図の違いがあやふや」
そんな不安を感じたことはありませんか?
新人監督やこれから現場を任される方にとって、図面の理解は避けて通れない大切なステップです。
この記事では、 床伏図・見上図・断面図 という3つの基本について分かりやすく解説します。
⸻
1. 床伏図(ゆかぶせず)

建物を「真上から見た図」が平面図といいます。
床伏図は平面図の一つで、足元を見た図面です
・各部屋の形
・柱や壁の位置
・開口部(ドア・窓)
・段差の位置
が一目で分かります。

👉 現場での活用例
・子墨出しのときに使います。(現場では見上げ図で墨出しすることの方が多いいかもしれません。しかし、床伏図の方が確実です)
※子墨出しとは?→親墨(建物の位置の基準となる墨)は墨出し屋さんが最初に出します。そのあと型枠大工が親墨から追って柱や壁の位置を出します。それが子墨です。
・床の高さを確認する
・シキサンの高さを決めるときに使います。
※シキサンとは?→コンクリートの表面は平らに見えて実はガタガタしています。そのまま型枠を建て込んでしまうと、建物の高さが変わってしまいます。そうならないために水平に高さ調整をすることをシキサンと言います。
・機械台や立ち上がりの位置を確認する
⸻
2. 見上図(みあげず)

床伏図とは違って見上げて躯体を表している図面で壁や柱は、もちろん載っていますし、梁やスラブのことまでわかります。
・スラブ(床でもあり天井でもある)の高さや厚み
・梁の形状
・開口の高さ
が読み取れます。

👉 現場での活用例
・型枠の形の拾い出しは基本、見上図を使います
・現場で型枠を建て込む際に使われる図面
⸻
3. 断面図(だんめんず)

建物を「途中でスパッと切った図」が断面図です。
・スラブの厚み
・梁や柱の高さ
・各階の天井高
が分かります。

👉 現場での活用例
・平面図でわかりづらいときの確認のため
・1階から2階などSLからSLまでの高さの確認(階高)
※SLとは→スラブレベルの略で、一階のSLのことを1SLと言います。階高の高さとは1SLから2SLの高さのことです。
・スラブ厚や梁の成を確認するときに使う
⸻
図面の使い分けフローチャート
「床の高さを見たい → 床伏図」
「梁の形状を見たい → 見上図」
「階の高さを見たい → 断面図」
「現場で今日1回、床伏図を開いてみてください。今まで気づかなかった発見があるはずです。」
まとめ
図面にはいろいろな種類がありますが、まずは 床伏図・見上図・断面図の3つを押さえること が第一歩です。
この3つを理解するだけで、躯体のどこを見るときに、どの図面を見るべきか?
が、わかるようになります。
📘 おすすめ学習コンテンツ
🔹 図面が読めるようになる基礎講座(note)
図面の基本記号・読み方・スケッチ解説までをまとめた入門セット。
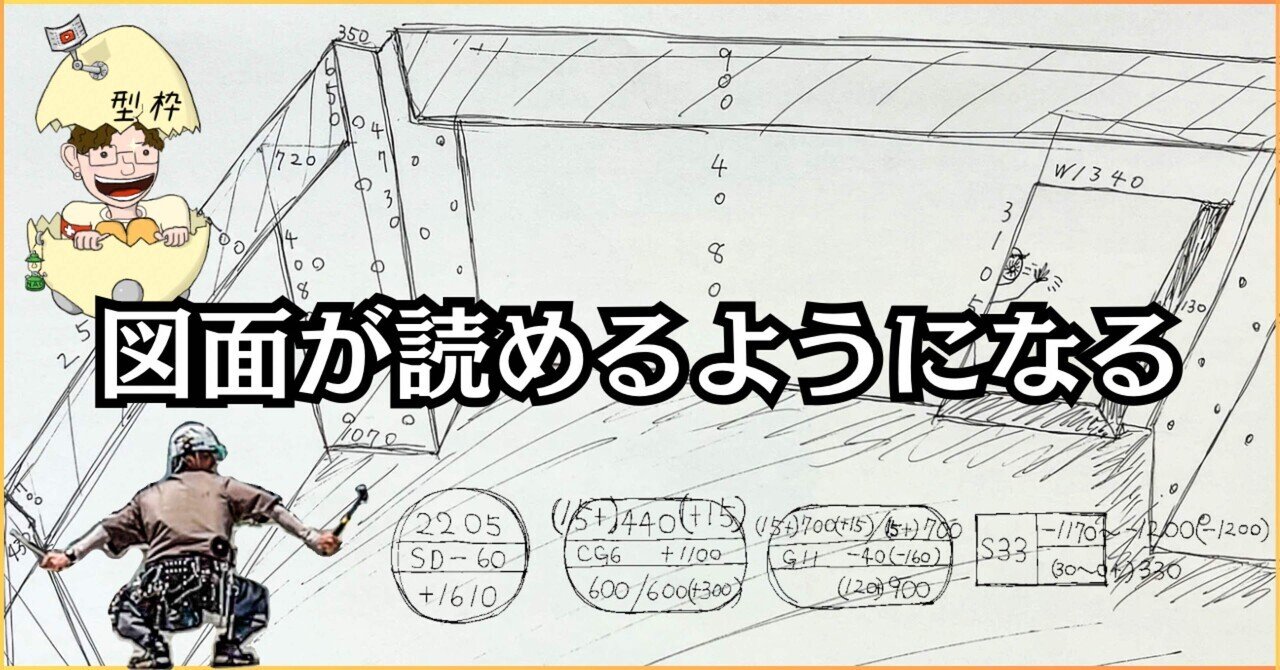
🔸 型枠拾い出し 完全マスターガイド(note)
拾い出しの流れ・加工図の描き方をまとめた実践教材。
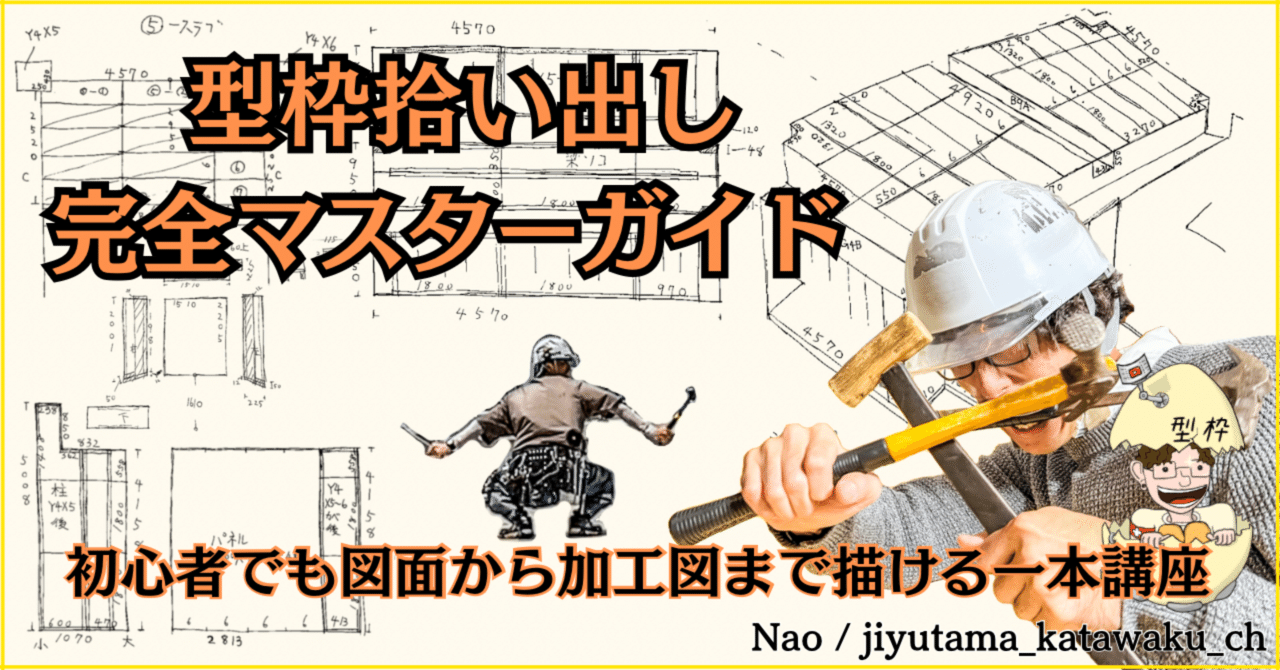




コメント