型枠大工として現場で働いていると、必ず必要になるのが「加工図の拾い出し」です。
この記事では、拾い出しの基礎となる材料の基本知識と、型枠加工図の考え方を整理していきます。
型枠に使う材料の基本


拾い出しの前に、まずは材料の呼び方や寸法を押さえておきましょう。
・ベニヤ(コンパネ)
現場によくある黄色いベニヤ
型枠を作るのに使われるベニヤ板。
現場や職人達は「ベニヤ」って呼んだりパネコと呼んだり、ニロク(2×6)やサブロク(3×6)さまざまです。
正確には「コンクリート型枠用合板」
型枠で使用できる合板はJASマークが付いているもの。
表面に黄色い塗装がされている合板はパネコート(表面ツルツル)
昔は生ベニヤと呼んでいた(塗装なしの合板)今は見なくなりました。
どうしてかは、わかりません。
転用があまりできないからかな?
[基本サイズ]
一般的に型枠大工さんが使うのは900×1800mm or 600×1800の2種類
現場ではサブロクとニロクと呼ばれていて、意味は1尺読みです→1尺=303
900は3尺1800は6尺=3と6でサブロク
600は2尺=2と6でニロク
昔は長さの単位が尺だったので、今はmやcm、mmです。
厚みは 12mm
・角材(桟木)サンギ
※地域によってサイズにばらつきがあります。ボクが話す内容は関東圏での話です。関西だとサイズもやり方も変わってくるっぽいです!
もう一つ型枠の材料で必要なのが桟木(サンギ)です
サイズ24×48
長さは3000や4000を使います。
たまに27×48の少し分厚いものも使うときがあります。
・定尺(ていじゃく)パネル
ベニヤ(2×6)と桟木で作ります。
定尺のベニヤの大きさのまま桟木を付けたもの(パネル)
600の幅のパネルを繋いでいって、最後寸法が合わない部分を必要な幅でベニヤをカットして補助の枠を作ります。
定尺パネルは基本何度も転用するものなのでカットしたりはしません。カットする必要があるときは補助を作ります。
加工図の見方


型枠加工図の絵は内側から見た絵なので、最初はみんな混乱します!
型枠はコンクリートの入れ物なのでコンクリート側から見た形が型枠の形です。ムズイです(笑)
躯体図で想像した柱の形と加工図の絵は逆なんです。
躯体を鏡に映して見えた形。
説明が激ムズです。www
コンクリートの中に自分が入って見える形です。
それが型枠の形
ここを正確に理解しないと加工図は描けません!
ここを飛ばしてしまうと詰みます。
10年以上のベテランの職人なのにここを理解していない人、結構いるので…
番付(ばんづけ)の理解
型枠を作ったら名前をつけます。
どこで使う型枠なのか、わからなくなってしまうからです。
その名前のことを番付と呼んでいます。
[番付の書き方]
図面上で通り芯があると思います(X1やY2など)
通り芯を使って番付を書いていきます。
柱の例
名前X6Y4柱
これでもいいのですが柱のどこの枠なのかがわかりません
それでは現場で困ってしまうので前後左右も書きます。
この「前後左右」が混乱のもとで、しっかり理解しないと、現場で混乱します。
型枠に正解なんてものはありません!
けど今までやってきて、こうした方が良い!
って思ったから、この考え方を教えます。
[前後左右の理解]
前後左右は見方によって意味が変わります。
どういうことなのか?を説明します。
まずは、図面で前後左右を決めます。
わからなくなってしまうので図面の向きのまま前後左右を決めます。
図面の上が前として図面の下が後ろとします。左右はそのまま右は右です。
この図面の向きのままあなたは前を向いていることとします。
ちょっとだけ問題を出します。
[問1]
あなたの目の前に柱があります。
型枠の番付が前と書いてあったらあなたから見てどこの型枠ですか?
柱の向こう側か?それとも目の前の今見える柱の場所?
もう一つ
[問2]
あなたは同じく図面の向きと同じ方向を向いています。右を向くと壁があります。
この壁の番付は右ですか?左ですか?
なんかはっきりわからない感じがしませんか?
わかりにくい原因は「どこから見ての前後左右なのか?」ってことです。
ここをちゃんと決めていないからわからなくなって、しまうんです。
柱の中に入って前後左右?
柱の外から前後左右?
壁の中から前後左右?
壁の外から前後左右?
ボクは
「コンクリートの中に入って前後左右を決めています」。
1番間違いが少ないです。
一階から上の建物の話で、地下工事は別です。
[答え合わせ]
[問1]
答え=柱の向こう側→柱の中に入って前だから
[問2]
答え=左→壁の中から見たら左だから
拾い出しは慣れるまで時間がかかりますが、ここを正確にできるようになると、どこでも加工図が作れるようになるので、拾い出しをPCなどでやるときも迷わずにできるようになります。
拾い出しを理解していないのに拾い出しソフトなどで拾ってもつまずくと思います。
まとめ
今回は「拾い出し入門編」として、材料の基本と番付の考え方を紹介しました。
これで拾い出しが始められます☺︎
📘 おすすめ学習コンテンツ
🔹 図面が読めるようになる基礎講座(note)
図面の基本記号・読み方・スケッチ解説までをまとめた入門セット。
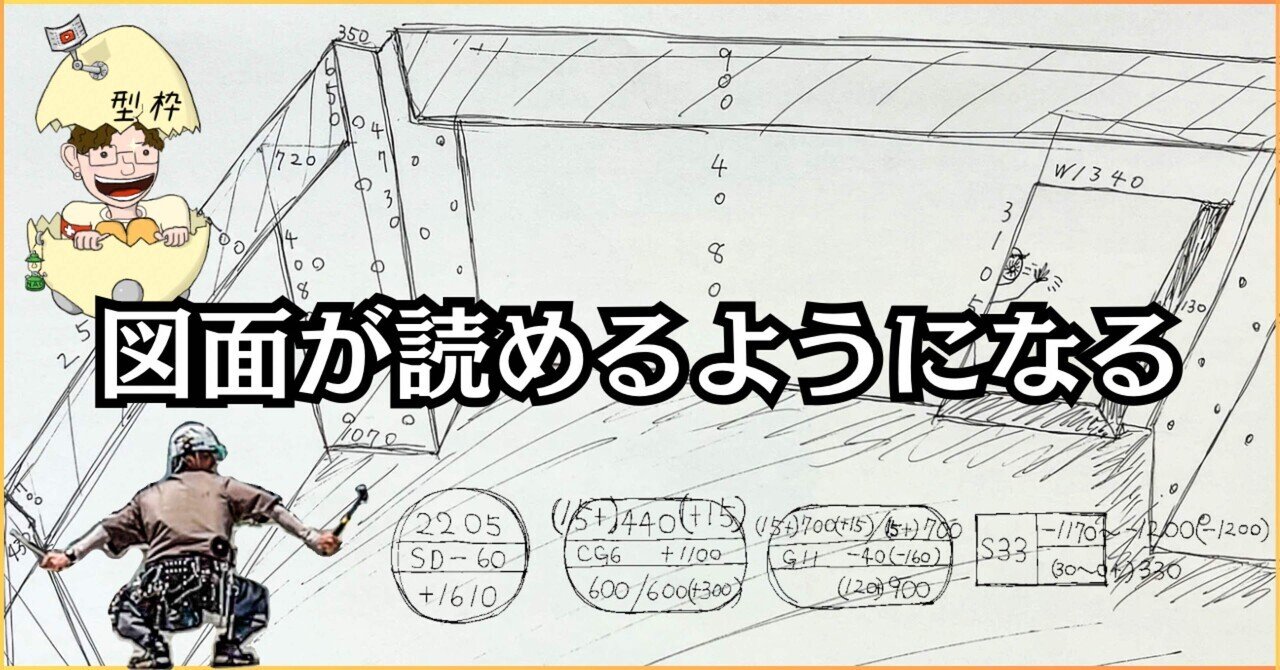
🔸 型枠拾い出し 完全マスターガイド(note)
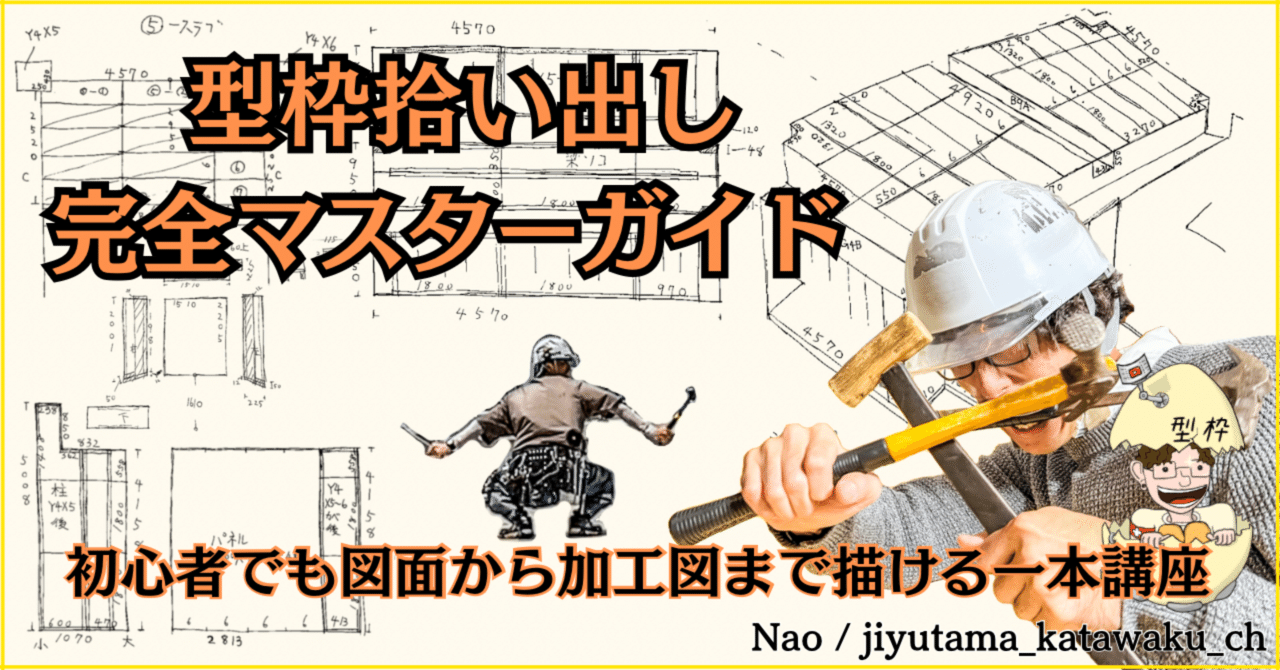




コメント