建築の図面を読むときに必ず出てくるのが「壁」や「柱」の記号、そして「寸法の拾い方」です。
この2つを理解できると、図面から現場の形をイメージする力が一気に伸びます。
今回は新人監督さんや若手大工さんに向けて、基礎の部分をわかりやすく解説していきます。
⸻
1. 壁の記号の読み方

壁は線のすぐ横に記号が書かれています。
・W〇〇(W15など)と書かれています。
構造体が150の厚みの壁ということです。
構造体とは→強度などの理由で決められている大きさ。
※絶対守らないとならない寸法です。
・W15の壁でも躯体は150より大きいことがあります。
「躯体」とは実際に作る形のこと
・壁の線のすぐ内側には点線が書かれているときがあります。
この点線の意味は構造体寸法よりふかしているということです。
「ふかしている」とは大きくしているということです。
👉 図面には「W=150」「t=100」といった厚さの指示がよく記載されています。
これを見落とすと現場で寸法違いのトラブルに繋がるので注意が必要です。
⸻
2. 柱の記号の読み方

柱は四角や丸で表されます。断面寸法が中に書かれているのが基本です。
・□(四角柱):例)□400×400 → 断面が40cm角の柱
・○(丸柱):例)φ300 → 直径30cm
・〇〇×〇〇というのは構造体寸法で、実際の現場の躯体はそこからふかしたりして寸法が変わります。
👉 柱は「通り芯」と「通り芯」の交点に配置されることが多いので、図面上で位置を確認するクセをつけましょう。
⸻
3. 寸法の拾い方の基本

図面には必ず「寸法線」が描かれています。これを正しく読めるようになることが大切です。
(1)寸法線の種類
壁柱梁などには芯があるのが基本です。
180の壁なら180の半分の90の位置が芯です。その芯の位置は、通り芯から追っていきます。
基準寸法:通り芯からの壁芯までの距離(例:1,000、3,000など)
・部分寸法:部屋や壁厚の細かい寸法(芯から90が壁の位置など)
・合計寸法:外壁から外壁までのトータル寸法
👉 まずは「大きい寸法 → 小さい寸法」の順で拾うと整理しやすいです。
(2)拾い出しの順番
1. 通り芯の間隔(建物の骨格)
2. 壁の厚み(W寸法)
3. 開口部(ドア・窓)の寸法
4. 柱のサイズと配置
こうやって順に拾うと、図面から建物の形を組み立てやすくなります。
⸻
4. よくある間違いと注意点
・1枚の壁なのに途中から厚みが変わることに気がつかないで間違える
・柱の寸法を図面の「〇〇×〇〇」で計算してしまう
・部分寸法と合計寸法が合わないときに「図面ミス」ではなく「読み違い」の場合が多い
👉 寸法は必ず 複数の位置で確認する のがコツです。
⸻
まとめ

・壁の記号は、その場所にできる壁の位置や厚さを示しています。
・柱は形と断面寸法で確認する
・寸法は「大きい寸法から小さい寸法へ」順番に拾う
壁・柱・寸法の基本を押さえることで、図面全体がグッと理解しやすくなります。
📘 おすすめ学習コンテンツ
🔹 図面が読めるようになる基礎講座(note)
図面の基本記号・読み方・スケッチ解説までをまとめた入門セット。
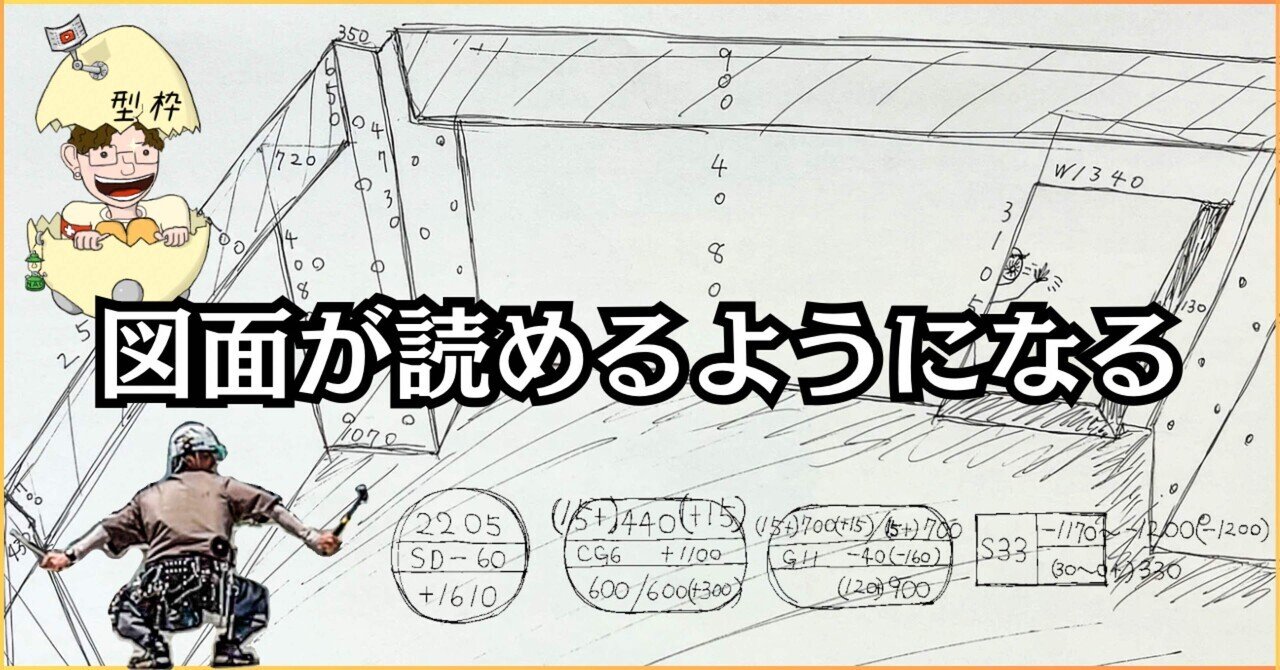
🔸 型枠拾い出し 完全マスターガイド(note)
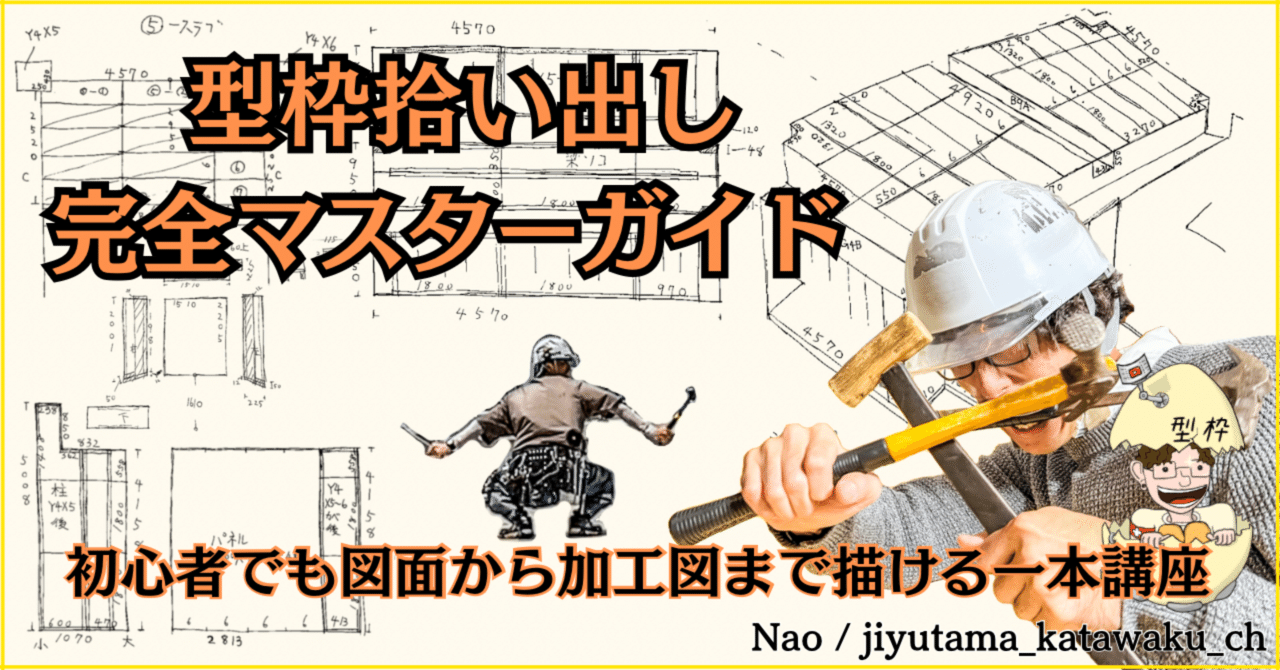
お知らせ用X(旧Twitter)じゆたま↓↓↓




コメント